
保護基金創設20年、商品先物委託者債権保護の歴史(中)
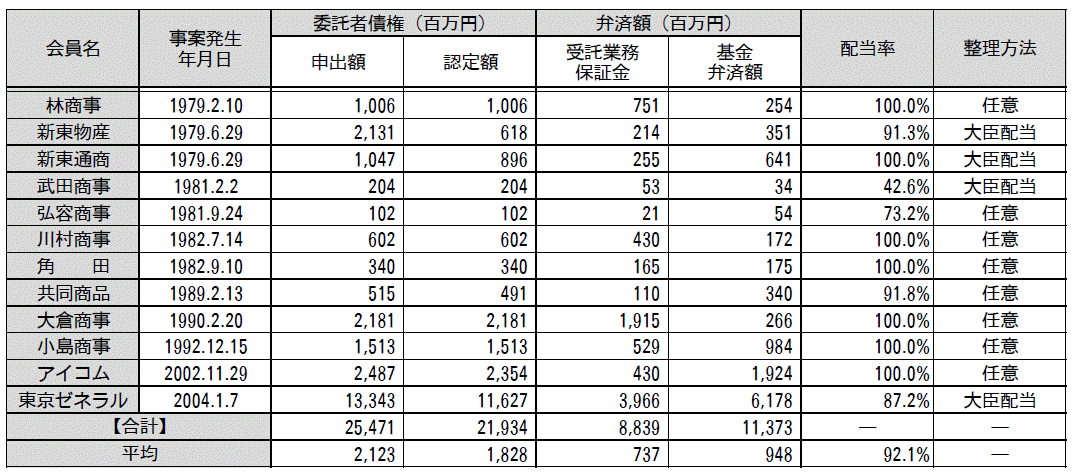
保護基金表
金融商品における委託者資産の保全は今では当たり前になっているが、導入当初は「なぜ顧客からの預りを他に持っていかなければいけないのか?」と疑問を呈する商品取引員もいた。社団法人として商品取引受託債務補償基金協会が設立されたのは1975年(昭和50)10月31日である。初代理事長はカネツ商事の清水正紀社長が務めた。以来、11社の弁済事案に立会い、業界のセーフティーネットとしての役割を果たした。だが大型弁済案件に関連して制度疲労が露呈し始めており、補償基金は2005年(平成17)5月1日に解散し、委託者資産の保全は日本商品委託者保護基金に引き継がれた。
2002年(平成14)11月29日、東京穀物商品取引所の農産物市場でアイコムの場勘定決済が不能となり破綻した。東穀取における違約の発生は82年12月の川村商事以来20年ぶりだった。破綻当時アイコムは東穀取に約3億5,000万円の受託業務保証金を預託しており、分離保管口座には指定信託等が義務付けられている35%は保全されていたが債務補償には全く足りず、補償基金の1号会員であるアイコムには代位弁済措置が適用された。これにより補償基金は約20億円を拠出した。
2004年(同16)1月7日には、前日に商品取引員の許可を取り消された東京ゼネラルが東京工業品取引所(現・東京商品取引所)で違約を発生させ事実上破綻した。東ゼネの違約は過去の弁済事案に比べ桁違いに大きかった。アイコムの委託者は1,000人ほどだったが東ゼネは4,000人の委託者を抱え、補償基金は弁済の上限を30億円としていたが、結局上限額一杯の拠出を余儀なくされた。しかも東ゼネの場合、帳簿上分離保管されているはずの信託が実際にはなかったことで、補償基金は責任準備金7億円を取り崩し弁済財源に充てている。
アイコムと東京ゼネラルという2社の大型弁済案件を経て、受託業務保証金制度の制度的な問題点が露呈し始めた。主な問題点は3点あり、①受託業務保証金制度、②分離保管制度、③共同補償制度―のそれぞれに問題が潜んでいた。
具体的に記すと、制度①は委託者債権の保全のため、商品取引員が委託者から預託された委託者資産のうち所定の計算により算出した額を自社の資産から分離して商品取引所に受託業務保証金として預託するものであり、商品取引員が経営破綻した場合には、委託者はこれに対して返還請求権を有しており、委託者債権の保全制度の観点では問題がなかった。
だが保証金のうち流動部分の算出方法が前月の平均建玉ベースの1カ月固定方式であるため、超過預託をカバーできない、状況によっては無用な資金の固定化を招くといった難点があり、結果的に直近の委託者債権に対応できないという問題があった。
制度②は委託者からの預り純資産から取引所への預託金(受託業務保証金及び委託取引証拠金)及び補償基金保証額を控除した額を、商品取引員の資産と分離して、信託期間への信託、金融機関への保証委託、銀行預託・協会預託により保全する制度だが、このうち銀行預託については預託銀行による相殺、一般債権者による差押さえ、商品取引員による流用等による資産の毀損が懸念されるなどの問題があった。
制度③は商品先物取引業界全体のセーフティネットとして構築され、委託者の保護を図ることにより商品先物取引に対する信頼性を確保する点で有意義な制度であるが、補償基金協会は任意加入・任意脱退可能であり、商品取引員の競争激化、二極分化により、拡大路線をとる大手事業者の一部には基金は中小事業者のための負担のみを共同で負うものという意識が強かった。また、1999年(平成11)10月から2号会員、契約商品取引員制度ができたため、1号会員からの脱退を容易にする懸念が生じていた。さらに1号会員の一部には、補償基金協会の弁済責任が1号会員の将来の不確定・無限な拠出責任(偶発債務化)に繋がる恐れがあるという批判も生じていた。
<以下、続く>
参照:保護基金表【PDF】
(Futures Tribune 2025年6月25日発行・第3367号掲載)
リンク
©2022 Keizai Express Corp.