
インド、デリバティブ市場の大躍進【上】
2025-10-15
屋台でPaytmを扱うイメージ写真(チャットGPT生成)
世界のデリバティブ業界団体である先物取引業協会(FIA、本部・米ワシントン)が公表した2024年における世界89取引所のデリバティブ取引(先物取引およびオプション取引)の取引量(総計・地域別・分野別・取引所別など) において、トップは昨年同様インドのインド・ナショナル証券取引所、2位がBSE(インドの旧ボンベイ取引所)だった。両取引所ともに株価オプションの取引量が際立っており、合計すると1,540億枚とデリバティブ取引全体の約75%を占める。世界最多の人口14億人を抱えるインドではあるが、2020年の段階では同国デリバティブ全体で年間100億枚と、アメリカの方が多かった。それがなぜ僅か4年で甚大な伸びを示したのか、インドの政策や経済をもとに特集する。
突然の高額紙幣廃止がもたらした電子決済の普及
2016年11月8日20時に、インドのナレンドラ・モディ首相が突如発表した高額紙幣の廃止は、国民にとって青天の霹靂であった。当時国内で流通していた9種のインド・ルピー札のうち、高額上位2種である1,000ルピー札と500ルピー札について、翌日(つまり4時間後)に法定通貨としての効力を失うと、インド国営テレビを通じて宣言したのである。
当時の紙幣流通状況を[額面]、流通枚数(億枚)、流通額シェアで振り返ると、
- [1] 1,252 0.5%
- [2] 383 0.1%
- [5] 3,447 0.7%
- [10] 3,624 2.8%
- [20] 440 1.3%
- [50] 1,046 4.3%
- [100] 1,570 17.5%
- [500] 1,571 47.8%
- [1,000] 634 38.6%
であり、つまり資金供給量の約86%を翌日から無効としたのである。
突然知らせを受けた国民にとっては驚天動地の極みであり、インド政府は一定期間内に廃止対象となった2種の旧紙幣を銀行や郵便局で新紙幣(新500ルピー札か新2,000ルピー札)と交換、または口座に預けることを要求した。また同時に現金の引き出し制限も課されたことで、翌日からインド各地のATMや銀行には長蛇の列ができ、大混乱したのは言うまでもない。
政府が実施したデモネタイゼーション(高額紙幣の廃止)には、インド国内に蔓延していた汚職の撲滅とブラックマネー排除による税収増、かつ偽造通貨の流通防止という目的があった。同時に現金依存度の高い国内経済をキャッシュレス経済に移行させる狙いもあったが、農村部や日雇い労働者は現金経済の態勢が続き、当初は混乱が広がっただけだった。このためGDP成長率は一時的に鈍化し、多くの中小企業が資金繰りに困窮する結果を招いたのである。
一方、政策効果の観点でも廃止紙幣の99%が銀行に戻ったものの、ブラックマネーの排除は限定的とされ評価は低かった。
だが副次的な成果が徐々に表れ始める。まず高額の旧紙幣を預金せざるを得なかった国民が銀行やATMに殺到したことで、銀行預金の総量が爆発的に膨らんだ。その規模は数十兆ルピーに及んだが、必然的に市中を巡る現金が一時的に激減したため、デジタル決済が一気に普及し始めたのである。
国営銀行や農村銀行は預金急増に直面し貸出余力が拡大した。余剰資金の運用効率については後年諸々の反省点が指摘されたが、金利の低下が進んだことで余剰マネーが証券市場に集まり流動性が高まった。
現金経済主体であった農村部や日雇い労働者についても、2014年に始まった「Jan Dhan Yojana(国民向け口座開設プログラム)」と連動し、次第にデジタル決済の波に取り込んでいった。具体的には同年に53%だった口座保有率が、16年のデモネタイゼーションにより紙幣交換を目的とする口座需要が一気に高まったことで、翌17年には保有率が80%超に上昇した。この結果、公共料金や給与支払いが銀行経由となり、政府給付金も口座振込みが主流化した。これにより政府の財政運営や社会保障政策にも、一定の透明性がもたらされたのである。
固定電話網の未整備がモバイルの爆発的広がりへ
インドでデジタル決済が広まり金融革命の域に到達した背景には、モバイル端末の普及と密接な関係がある。19世紀の電信、20世紀の固定電話は国内で限られた層にしか普及しなかったが、1990年代以降、携帯電話の登場で状況は一変した。固定電話の保有が限定的であった分、プリペイド方式の携帯電話が低所得層にも普及し、固定電話を飛び越える「リープフロッグ現象(※1)」が起こった。
※1[既存の社会インフラが十分に整備されていない新興国や途上国において、先進国が段階的に発展させてきた技術やサービスを飛び越え一気に最新技術が普及する現象]
2010年代にはスマートフォンが低価格化し、2016年のReliance Jio(リライアンス・ジオ:インド最大の通信事業者)参入で通信料金が激減した。第4世代移動通信システム(4G)が国民的インフラとなり、SNSやモバイル決済が爆発的に普及したのである。現在は5Gが都市部から拡大中であり、Aadhaar(生体認証ID)と政府主導の統合決済基盤UPI(Unified Payments Interface(※2))がスマホに統合され、銀行口座とモバイルアプリが直結した。
※2[インド国立決済公社(NPCI)が2016年に提供を開始した、銀行口座間のリアルタイム送金サービスを提供するプラットフォーム。モバイル端末から24時間365日、即時送金や決済が可能]
提供初年である16年に月間数百万件規模だったUPI決済は、23年に同1,000億件超へと拡大。これは世界最大の規模であり、かつて現金大国と呼ばれたインド経済がデジタル決済大国へ転身した象徴といえる。こうして少額決済まで電子化が進んだ結果、インド経済の取引履歴がデータとして蓄積され、信用スコアや融資審査にも活用され始めている。
インド国民の生活基盤となった「Paytm」とは
インドのキャッシュレス革命を象徴するのが電子決済システム「Paytm」である。創業者ヴィジャイ・シェカール・シャルマは、中国アリペイのモデルを研究し、銀行カードを介さない形でのモバイルウォレットを基盤に据えた。
2013年のサービス開始当初は携帯プリペイドチャージから始まったが、公共料金や買い物、映画チケットへと拡大していった。15年にアリババグループ(中国)のアントが出資し、技術と資金の提供を始めた。これが16年のデモネタイゼーションで利用者は急増し、UPIと結びついたことでさらに普及した。
Paytmはこれを早期に採用し、利便性を高めた。さらに政府は零細店舗や屋台にQRコード導入を奨励し、街角の屋台や果物売りも電子決済に対応し始めた(イメージ写真)。市中の現金不足で売上を落とした小規模業者が、Paytmを通じて再び客を呼び込む事例は各地で相次いだのである。
前述のとおりPaytmは決済にとどまらず、鉄道チケットの予約や、さらには保険や投資まで生活全般にサービスを広げたことで利用者はPaytmのみで日常生活をカバーでき、都市部のみならず地方でも欠かせない存在へと成長した。
影響は当然企業活動にも及び、中小企業は売上管理をデジタル化できたことで、取引履歴が融資審査の信用資料となった。従来、信用情報が乏しく資金調達に苦しんでいた零細事業者にとって、Paytmの利用実績は与信の足跡となり、経済の透明化を促進したのである。
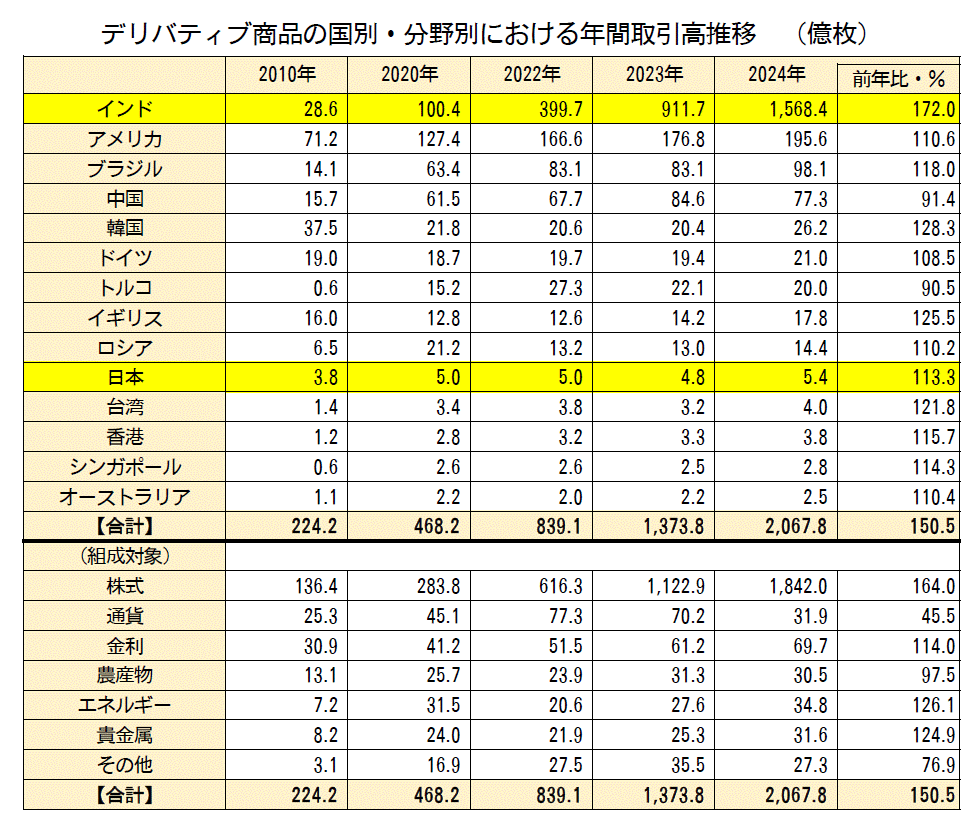
リーマンショックを経て“新興国の星”に
インドで金融市場が伸びた背景には、2008年に発生したリーマンショックの影響も関係している。先進国に深刻な打撃を与えたリーマンショックだが、インドの影響は比較的小さかった。理由は金融機関の外貨依存が低く、米国証券化商品への投資が限定的だったためである。
リーマンショック直後、輸出依存度の高いIT産業や繊維産業は受注減に苦しみ、GDP成長率も一時的に6%台へと鈍化した。しかし政府は大胆な財政出動とインド準備銀行(RBI)の迅速な金融緩和を実施した。内需主導の経済構造が功を奏し、2009年には早くも回復基調に転じた。欧米依存の輸出モデルに比べ、インドは巨大な国内市場を背景に消費需要が旺盛だった。リーマンショックは、インドに「輸出依存ではなく内需とデジタルで成長する」という方向性を明確にした転換点だった。その後の高成長は人口ボーナスを背景としたものだけでなく、制度的安定性と金融技術革新が融合した結果でもある。世界が混乱に沈む中で、インドは“新興国の成長モデル”として存在感を強めたのである。
参照表:デリバティブ商品の国別・分野別における年間取引高推移(億数)※PDF表説明:世界国勢図絵第36版(矢野恒太記念会)「デリバティブ取引の取引高推移」を引用
FIAサイトの統計情報より、本紙が集計したデリバティブ取引集計表も参考にした
(Futures Tribune 2025年9月26日発行・第3386号掲載)
リンク
©2022 Keizai Express Corp.